受付時間 9:00~18:00
#177 「笑いは世界を救う」
幼いころは内気で大人しい子でした。よく父が職場の部下たちを連れてきて家で宴会を開いていましたが(母親が接待で結構大変な思いをしたと思います)私はいつも陰に隠れていました。早く帰ってくれないかなと思いながら。子供のころから臆せず堂々と大人と話す子がたまにいますが、とてもじゃなかったです。せめて恥ずかしそうでも、ニコニコと父親にくっついてその場にいるような子ならよかったんですが、まるで隠れてしまっていましたから。たまにわざわざ探しに来て遊んでくれる部下の方もいました。
でも大人しくても、ユニークで一風変わった子だったと記憶しています。自分でもそれを自覚していました。とにかく家族の中ではふざけるのが好きでした。言葉遊びが好きで、面白い響きの新しい言葉を仕入れると、日がな一日その言葉をぶつぶつ繰り返していたのを思い出します。当時のソ連の政治家の名前をテレビで聞きかじって、それをブツブツ繰り返していると母に笑われました。その「言葉遊び好き」の性質が今の「令和のダジャレおじさん」として引き継がれているのでしょう。
「そうか、このような『変な子供』は思春期には鳴りをひそめながらも続いて、大学生あたりで開花したという流れになるのだな」と予想した方も多いと思いますが、基本的に内気な性格は変わらず、成長に応じて、その活動する範囲が広がってきたということでしょうか。つまり内向的だけどよく活動する人間、矢野健太郎が形成されていくのでした。
その中で自分の信条として根付いていたのが「人を笑わせてなんぼ」といものです。子供のころはよく家族を笑わせていましたが、それがもう少し一般大衆相手に広がってきたのです。それなら、お笑いの道に進めばよかったと思われる向きもいるかもしれませんが、そういう感じでもないのです。そこに必要なのは「常時面白い」というものではなく、「突発性」と「意外性」なのです。つまり内向的な普段とのギャップが大切なのです。

今はお世辞にも(お世辞にも?)内向的とは言えません。なんだか45歳を境として一気に性格が外向きになってきたと感じています。45歳に何が起こったのか。福祉介護の世界に入ったのです。記念すべき出来事でした。福祉介護は人間を変える・・・とまで言えば大袈裟ですが、少なくともどんどん人と話をする(話をせざるを得ない)ようになります。人の様子を観察し、コミュニケーションをとろうと試みます。卵が先かニワトリが先かの議論ではありませんが、とにかくその時期を境として、私は「内向的で変な人」から「外向きで変な人」に変わったのです。「変な人」は変わってないのか・・・・
いやいや、「変な人」はさらにパワーアップしました。それは一つの私の人生観かもしれません。大きな人の流れに飲み込まれるのは嫌、やっぱり自分は「変な人」として(目立っても目立たなくても)個性豊かに生きてゆきたいのです。そしてその中でとても重要なキーワードが「笑い」です。「人を笑わせることは、人を幸せにすること」+と信じています。まずは人が幸せになったうえで自分も幸せになりたい(そうじゃなきゃ自分だけが楽しんで幸せでどうするの)。笑いながら不幸を感じる人はそうそう多くないと思います。世界での国と国、人と人の関わり合いが「笑い」をベースにしていれば、戦争なんて起こりようがないと思うのは私だけでしょうか。「笑わせてなんぼ」「笑ってなんぼ」そして「笑いは世界を救う」です。
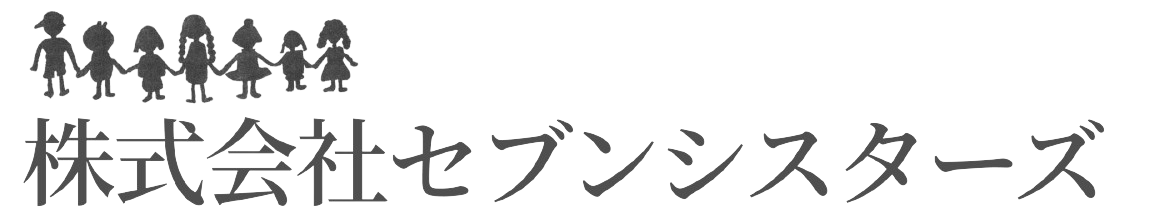








コメント