受付時間 9:00~18:00
#137 「かっちり覚える言葉、ざっくり覚える言葉」
最近は小学校から英語を習うようになりましたが、昔は中学に入って初めて英語に接することになり、初めて習う母国語以外の言葉に、多かれ少なかれ戸惑っていたと思います。私もその一人でした。そしてほとんどの生徒は、四角い帳面に定規で線をひいて、左側に新しく習った単語、真ん中に品詞、右側にその意味とかを書いて、右を隠したり左を隠したりしながら英単語を覚えていったはずです。「働く」はWORK、「歩く」はWALK、紛らわしいなあ~とか「水曜日」はWEDNESDAY、「木曜日」はTHURSDAY、覚えにく~とか、それぞれ苦労して独特な覚え方を編み出しつつ覚えていきます。そしてそれは、暗記力と脳の容量を競う作業以外の何ものでもありません。そのうち、脳の中がいっぱいになって「今日はもうこれ以上覚えられないよ~」なんてことになります。
私自身の勉強を振り返ってみると、まったくもってこのようなやり方をしていました。ただ、その時その時に「脳の容量」は一時的にパンクしますが、何せ10代の前半、まだまだ脳細胞は毎日のようにどんどん増えていきます。だから「1000語覚えたから、これ以上は脳が受け付けません!」なんてことはないのです。そして、まだ若いころに頑張って覚えた単語なので、だいたいは「引き出しをうまく開けられれば」出てきます。
それからうん十年の時が流れ、私は60代の手前から再び英検の試験を受けようと思い立ちました。そして再び、今度は少し難しめの英単語や英熟語を覚え始めましたが、同じようなやり方(ノートや単語カードを作って暗記する)では、一時的には覚えても、次の単語を入れると、まるで豆鉄砲のように前の単語が出ていきます。いわゆる短期記憶の劣化ですね。やっぱり60代が10代の方法ではダメ。60代は60代の覚え方をしないと若い時の勉強のようにはいきません。
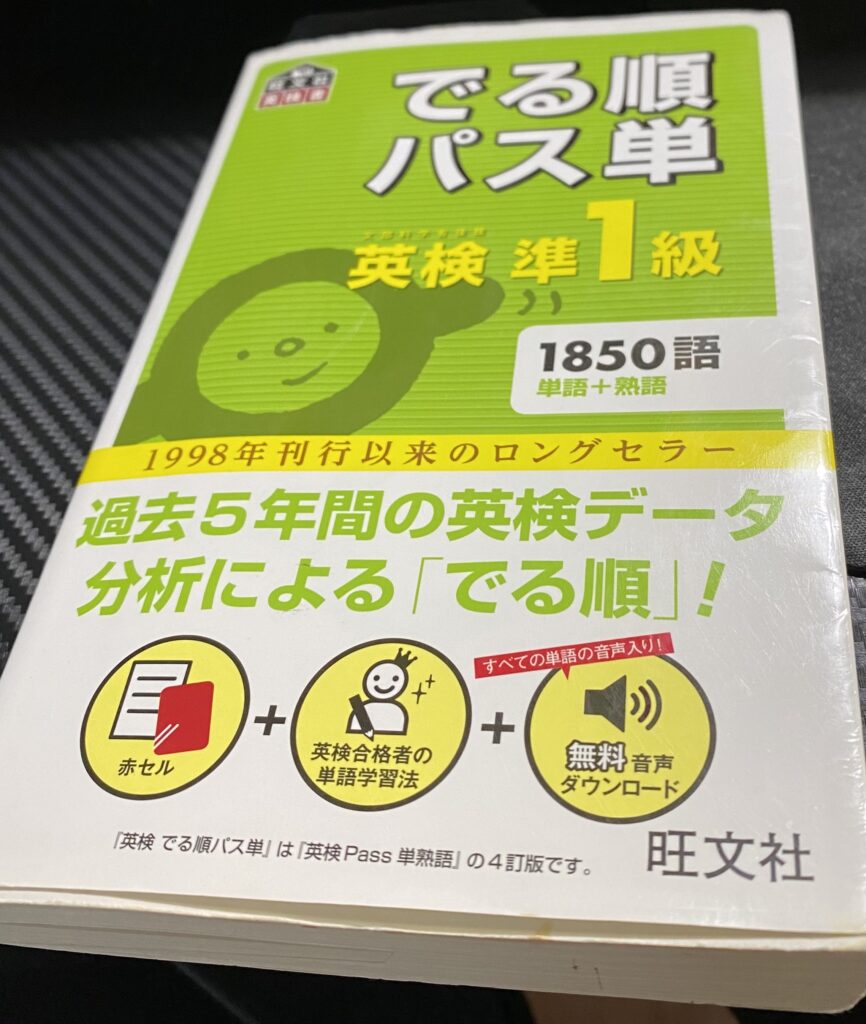
一方、ちょっと上級の単語や表現でも、ずっと忘れないで身についているものもあります。それは何かと言うと、海外駐在時代に実際に意味も分からずに耳から聞いて、雰囲気で覚えた言葉です。かっちりではなく、ざっくり覚えた言葉です。
例えば、シンガポール人がよく使う”how come~”という表現がありますが、こんなこなれた表現を学校で習わなかった私は、最初何のことだろうと思いながら、その場の雰囲気から「これはwhyではないか」と推測して、見よう見まねで使ったら通じていたというものです。”no wonder~“なんかもそうです。”jeopardize”なんて難しい単語は商売をしなきゃ一生覚えることはなかったでしょうし、”touch wood”って何なんだと思いながら、しぐさや表情を見ているとなんか縁起の悪いことを言っている時に使ってるなあと想像しました。ちなみにこれは日本語では「くわばらくわばら」と良い訳し方があります。
こんな風に目と耳から入って想像しながらざっくりと覚えていった言葉は、いつまでも残っているのです。これは記憶の世界の「手続き記憶」と似ているかもしれません。一方かっちりと左脳で覚えて海馬にため込んだ言葉は、残念ながら年と共になかなか定着しにくくなるのです。これは「エピソード記憶」あるいは「意味記憶」でしょうか。ということで今日は記憶に関する研究発表でした。いや、違うでしょ。何の話でしたっけ?
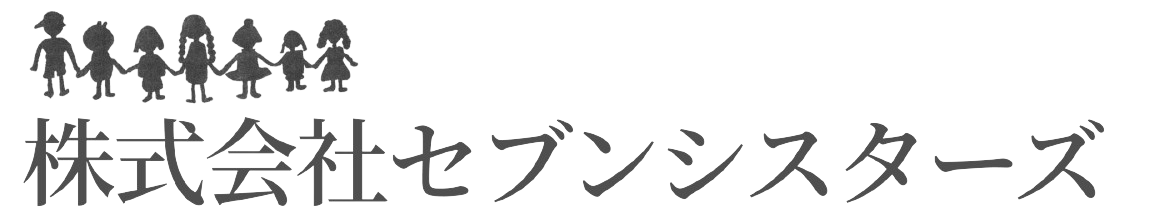








コメント