受付時間 9:00~18:00
#135 「認知症介護相談窓口『プロジェクトK』」
名前はNHKの番組のパクリやんと言われたら弁解の余地もありませんが、これはあくまで思い付きの「仮の名前」だし、所詮、小さな個人企業がしていることなのでお許しください。
最近、親族関係で認知症に関する相談を受ける機会が複数回あり、主に電話でのやりとりにかなりの時間をかけています。そのうち、キーパーソン(家族)、私の方から相談する人、ケアマネさん、地域包括の相談員さんと「基点」が増えていって、その「点」同士がいろいろな結ばれ方をしていって「面」になっていくという、まさにチームとしてのネットワークが出来上がってきます。認知症に限らず、社会福祉課題の多くはこのような「ネットワークを作っていく作業」から始まり、チームとしてその解決が図られていくのが通例だと感じています。
私も認知症介護に関しては長らくかかわってきたほうだと思っています。現場の介護職員、現場の管理者、見守り支援や相談職、研修講師など役割は変われども、認知症介護ということだけを取り上げてみると、もう20年来のかかわりになります。では、その中で私がもう認知症介護に関して何でも教えたりアドバイスしたりする立場にあるかといえば、とてもそんなことは言えず、この分野を深めるということについて言えば、いつまでも目的地にたどり着かない長い長い旅のようです。

学びの要素の中には、「知識」「技術」「価値」の三つの要素があるとよく言われます。この認知症に関する相談は「知識」「技術」だけを答えていっても解決しないことが多いように思えます。認知症ケアはよく全人的ケアと言われる所以で、どうしても「価値」の部分が大きくなります。しかし、相談を受ける人が「それは人として・・・」「人として考えたら~のほうが・・・」などのアドバイスを受けたとすると、どこかの宗教の教祖さんに教えを賜っているような感じで、きっとあまりいい気がしないように思います。
ですから、認知症介護の相談と言うのは、逆にあまりアドバイスをしない方がいいのかもしれませんし、かなり進め方が難しいものと言えます。質問に答えるというより、「何を望むのか、どうしたいのか」を地道に当事者、家族から引き出す作業が大きいのかなと思います。そして、その思いに寄り添うためにネットワークを作って、チームで解決していく、これこそ相談職の役割ではないかと思います。
大学の偉い先生や、その分野でしかわからない専門的な知識(弁護士、行政書士、医師など)や、ましてや教祖でもないから、この相談をビジネスにするのはやりにくいのです。「これに対してこの答えがあります」というものではないですから。
本当は、このような相談は全部無償で対応してもいいと思う気持ちもありますが、やはりそこは「福祉事業」という介護保険ではない、他の制度にもかかわらない、プライベートビジネスとしてあえて挑戦している会社ですから、ほどほどの相談支援料と言うものをとっていこうかなと考えています。どのような形態でどのような料金体系にするかはよくよく考えて行こうと思っています。しかし組織を大きくしようという気はさらさらありませんので、相談員は矢野健太郎一人です。数(マンパワー)に限りがありますので、品切れ(受け入れられない)場合はご容赦ください。安売りスーパーか。
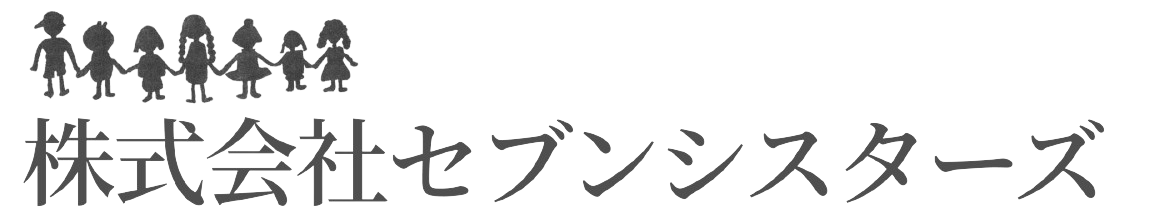








コメント