受付時間 9:00~18:00
#129 「記憶の記憶は記憶違い」
以前、NHKの「ヒューマニエンス」という番組で「記憶」がトピックである回を録画してあったのですが、昨夜、それがまだリストに残っていることを発見し、2回目を見ました。すると再度、新鮮な驚きがあり、脳科学とは実に面白いと再認識するとともに、「記憶」に関する記憶がすっかり薄れつつあったことを実感したのでした。
ですので、今回は備忘録的にここにまとめておいて、ある意味、「永久保存版」のようにしておきたいと思ったのですが、果たして昨夜の今朝でもうまくそれらをまとめられるかと言えば、正直自信はありません。
まず、私たちはよく「記憶違いだった(汗)」という場面に出くわします。私も昔は「いいえ、それは違う。絶対に〇〇だった」と頑固に言い張っていましたが、最近は自分の記憶は絶対ではない、いやむしろ自分の記憶の方が間違っていると思わざるを得ないようになってきました。それくらい、自分の記憶の方が「記憶違い」であることが増えて、その事実を知って愕然とすることが増えてきたのです。
しかし、記憶違いを生む科学的なメカニズムがわかり、少し安心した次第です。人は今この瞬間に見聞きした事実を、いろいろな要素に分類して一瞬にして海馬に記憶します。それらの要素が一つの星(点)だとすると(しかしその一つの星(点)自体が実に何千、何万もの違う情報が合わさったものです)その星をつないであたかも「星座(線)」のようになったものが、その時の記憶として残り、そして安定した記憶は長期記憶として大脳皮質に移されるということです。そのような「星座」が海馬や大脳皮質の中には無数に入っているので、これをだいぶたってから想起するときに、その星座に、うっかり他の星が紛れ込んで、つまり他の星(点)とうっかり結んでしまって、「新しい星座」として固定されてしまう。それが「記憶違い」の記憶として発出されるということのようです。

つまり、自分の記憶違いは、自分のうっかりぽっかりではなく、自分がそのことを重要視していなかったからでもなく、科学的に証明される「脳の働きのバグ」とでも言いましょうか。こうして理屈として考えると、なんとなく、自分は「堂々と記憶違いができる」と言えないでしょうか。あ、それはちゃうか。
というか、もうこの「記憶違い」のくだりだけで、これだけの文量になってしまい、ちょっと脳がつかれてきましたのであとは次回にします。お楽しみに。ただ、次回まで「記憶の記憶」が続いているかどうかは保証しません。つまり「記憶の記憶の記憶違い」が起こるかもしれません(ああ、ややこしや)。それよりなにより、実はブログ#008に「記憶」というタイトルのブログを既に書いていたようです。おそらく同じようなことを書いていたと思いますが、面倒くさいので確認はしません。
このブログを終わる前に、いつ来るかわからない次回の「記憶(つづき)」のブログのために、ポイントだけを書いておきます。
・「忘れる」のではなく「取り出しにくくなる」
・「忘れる」ことは脳の戦略的な、前向きな対策
・脳細胞間で情報と情報をやり取りしてつなげ、記憶を形作っている部位が「シナプス」であるが、そのシナプスを食ってしまう物質が貪食細胞「グリア細胞」である。しかし、その記憶を食うのは、むしろ記憶の方が「食われるのを望んでいる」。
・人は一日のうちに経験したことを、夜の睡眠の中で強化させて、記憶として根付かせている。だから睡眠は大事。
ということで、以上。脳科学の先生、もし何か間違っていたら教えてください。
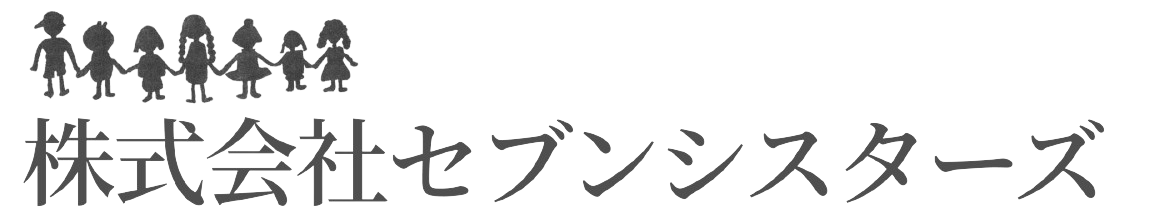








コメント