受付時間 9:00~18:00
#157 「行き当たりばったり」
性格からか、何でも先に先に計画する傾向にあるようです。昔からそうだったのでしょうか、いつかからかそうなってきたのでしょうか。その辺の記憶はあいまいですが、どうも気が付いたら矢野健太郎という人間はそういうことでした。冷蔵庫の中を見て、翌日の献立を計画するなんてのは序の口で、500円玉貯金が貯まったあとの使い道リストを作るとか、来年3月の旅行についてあれこれ細かく調べてほくそ笑むとか枚挙にいとまがありません。地域活動で補助金を受けるための年度末までの事業計画とか、ある程度先までの計画がないと困るようなものは仕方ありませんが、遊びごとや日常生活のことまで計画してしまう、いや、計画がないと落ち着かないのはやはり性格からかもしれません。
会社という組織に属してきた人は、ある程度そういった「くせ」が身についてしまっているのでしょう。私は東南アジアの極小支社でも一応「一国一城の主」でしたし、支配人会議の場などでは社長や常務を前にして「えーわが社の中長期販売計画を申し上げますと・・・」なんていっぱしにやってきましたし、そういうのも「くせ」の形成に一役買っているかもしれません。試しに定年退職した高校の同期に聞き取り調査をしてみましょうか。面倒くさいからやりませんけど。
でも、妙に心をくすぐるのが「行き当たりばったり」という言葉です。なんかいいなあ、やってみたいなあ。細かいことは忘れましたが、中学生のころ読んだ下村湖人の「次郎物語」の中に、次郎が「無計画の計画」という旅に出る場面があります。ちょっと魅力的な言葉ですよね。
「行き当たりばったり」はだいたい、あまりいい意味では使われませんが、これをプラスに変換して考えれば、それは非常にパワフルなワードになるような気がします。なんせ「行き当たりばったり」でも何かに対応できる力というのは相当の実力がなければ無理です。「臨機応変」ともちょっと違うこの言葉は、下村湖人さんの「無計画の計画」という解釈が一番当たっているでしょうか。そこには、多分に遊びの要素がつまっています。

大学卒業の時に、多くの学生が海外旅行とかするのに反し、私は「青春18キップ」を使って日本一周各駅停車の旅をしました。楽しかったですね。2回に分けて、第一回は東日本編、いったんうちに帰った後、二回目は西日本編でした。文字通り北海道は函館から九州は鹿児島までをぐるっと各駅停車で回ってきました。行程は全部で20日くらいでしたでしょうか。その時の旅が今までの人生では唯一、「行き当たりばったり」に近かったかなと思っています。青森に行ったときは急に恐山に上りたくなって(結局、途中で大雪のために断念しましたが)最寄りの大湊まで行ったのは、まさに「行き当たりばったり」で決めたことでした。
この短い人生、もうそろそろ第3コーナーを回るくらいのところに来ましたかね。最後まで計画、計画ではつまらない。ちょっと「無計画の計画」の旅に出てきたいと思っています。前回が「青春編」だったら今回は「錦秋編」か「成熟編」か。ま、名前はなんでもいいや。
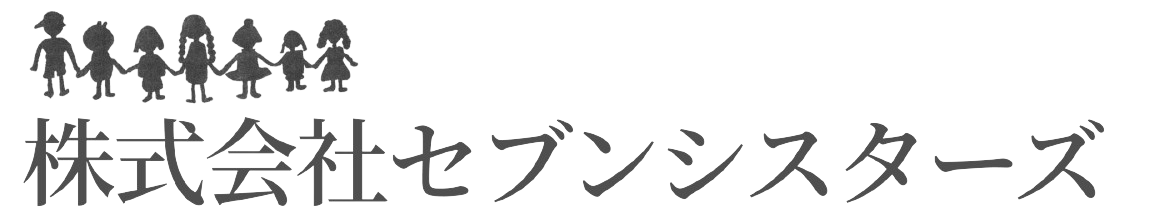








コメント