受付時間 9:00~18:00
#139 「優先順位」
年を取ると、次第に「時間」というものが自分の価値観の中でも大きな割合を占めるようになってきます。ウルトラマンのようにカラータイマーがピポンピポン・・・と鳴るとこまではいっていないにしても、人生の残り時間というのを気にし始め、また「自分が今の健康状態で、そして認知機能を維持しながらどのくらい過ごせるのか」ということが無性に気になってきます。
先日、とある研修で「会社を運営するための大切な経営資源とは」というあまり専門分野ではない講義を「はったり」もかましながら行い、その中で「ヒト、モノ、カネ」という経営資源の3大要素を強調してきました。そこで、それを私の今の気持ちに合わせて「私の生活資源」ということで言うと、さしずめ「ヒト、ジカン、カネ」だなと思いました。
まず「モノ」については、当然、これからどんどん増やしていくというのはちょっと違うと思いますよね。しかし新しいものを買いたいという欲望はつねにありますので、一つ買ったら二つ捨てるという感覚でいます。時には思い切って一時に大量に捨てることもあります。一方「モノ」に対する考え方については、多分に個人個人の価値観が違いますので、あくまで私個人の場合はということです。
このように「モノ」はあるときから「ふやす」から「へらす」に変わってきています。ただ、「カネ」に関しては、「へらす」という訳にもいきません。そもそも「へらす」ほどの蓄えはないという問題もありますし、常に一定の量のお金は必要だからです。しかし、少なくとも「今からどんどん増やす」というものではないことも確かです。まあ増やしたくても増えませんけど。「カネ」については「たもつ」というところでしょうか。
「ヒト」が死ぬまで大切なものであるという考えに異存はないと思いますが、問題は「ジカン」です。人は科学的に言えば、生まれた瞬間から死ぬまでの時間のカウントダウンが始まっているとも言えますが、20代や30代で「死までの残り時間」を意識している人は、哲学を専攻している学生さんくらいでしょう。しかし、私のようにそろそろ制度上の高齢者の仲間入りをするという年齢になってくると、どうしても「残り時間」を意識します。白熱したサッカーの試合で、1点差で負けている時に残り時間を気にするようなものです。
今を精一杯生きているとき(福祉の授業をしている時や居場所活動をしている時など)は残り時間のことなど忘れていますが、本屋や図書館に行ってまだまだ読んでいない本や読みたい本がべらぼうにあって愕然とするときや、紀行番組を見ていてここに行きたい、あそこに行きたいと思うときなどは、やはり急に残り時間が気になったりします。

それを考えるときに効果的なのが「優先順位」の存在です。もちろん残り時間と言っても「死ぬ瞬間」までの時間では図れません。つまりは何らかの病気で寝たきりになった時、認知機能が落ちて理解力がぐんと落ちてしまった時などは本を読んだり、旅行に行ったりはなかなか困難になるからです。健康寿命があとどのくらいあるかを見通してそこから逆算しながら優先順位を決めるという、なかなか高度な作業が必要になります。
いよいよ人生も最終段階になったと思うときに決める優先順位のリストが、すなわち「バケットリスト」ですよね。映画のように、バケットリストがどんどん実現していくと素敵だなと心から思います。(写真:どこに飛んで行こうか?)
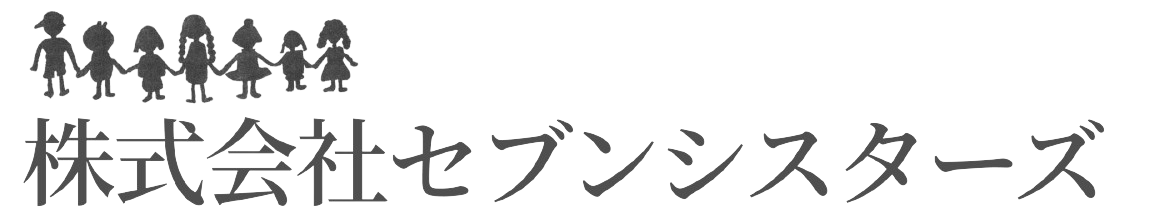








コメント