受付時間 9:00~18:00
#136 「べらぼう~蔦重栄華の夢噺」
NHKの大河ドラマは、お世辞にも大ファンだとは言えません。「はまる」ときにははまるので、さて今回は面白いかなと初回から見始めることが多いのですが、ほとんどは第2話、あるいは第3話あたりで脱落しています。最初から最後まで見切ったドラマは覚えている範囲では二つしかありません。一つは三谷幸喜さんの「新選組!」で、もう一つはつい最近の「どうする?家康」です。この二つが特段、世間的に好評だったというわけではなさそうだし、逆に「史実とかけ離れている」や「ミスキャスト」などとどちらかと言えば否定的に言われていたように記憶しています。しかし、見ている内にたまたま、はまってしまったということかもしれません。
しかし、今回の「べらぼう」は少しその通例を覆すものであると思います。まず第一回目の「つかみ」が強烈でした。「吉原炎上」の大火から始まって、物議になったシーンが出てきたりして完全に初回からわしづかみにされました。NHKの戦略勝ちですね。
そして、このドラマにはまったもう一つの理由は、テーマが「文化」であり、しかもその舞台が江戸の花街の代表格、吉原です。今までは、「政治」とその中に展開する家族の葛藤や恋のお話しが主流だった(と思います)ので、ちょっと異色であることには違いありません。そして単なる吉原の花街文化ではない、その花魁さんたちの着物の色、遊郭の中の装飾や出版した細見本の中身の色など、本当に色遣いが鮮やかなことに完全に魅せられてしまいました。まさにこのような極彩色にあふれる街に一気にタイムスリップした気になります。自分が絵をかくときに「色」には本当に細心の注意をむけますので、このような色遣いの世界に入るのは願ったり叶ったりです。
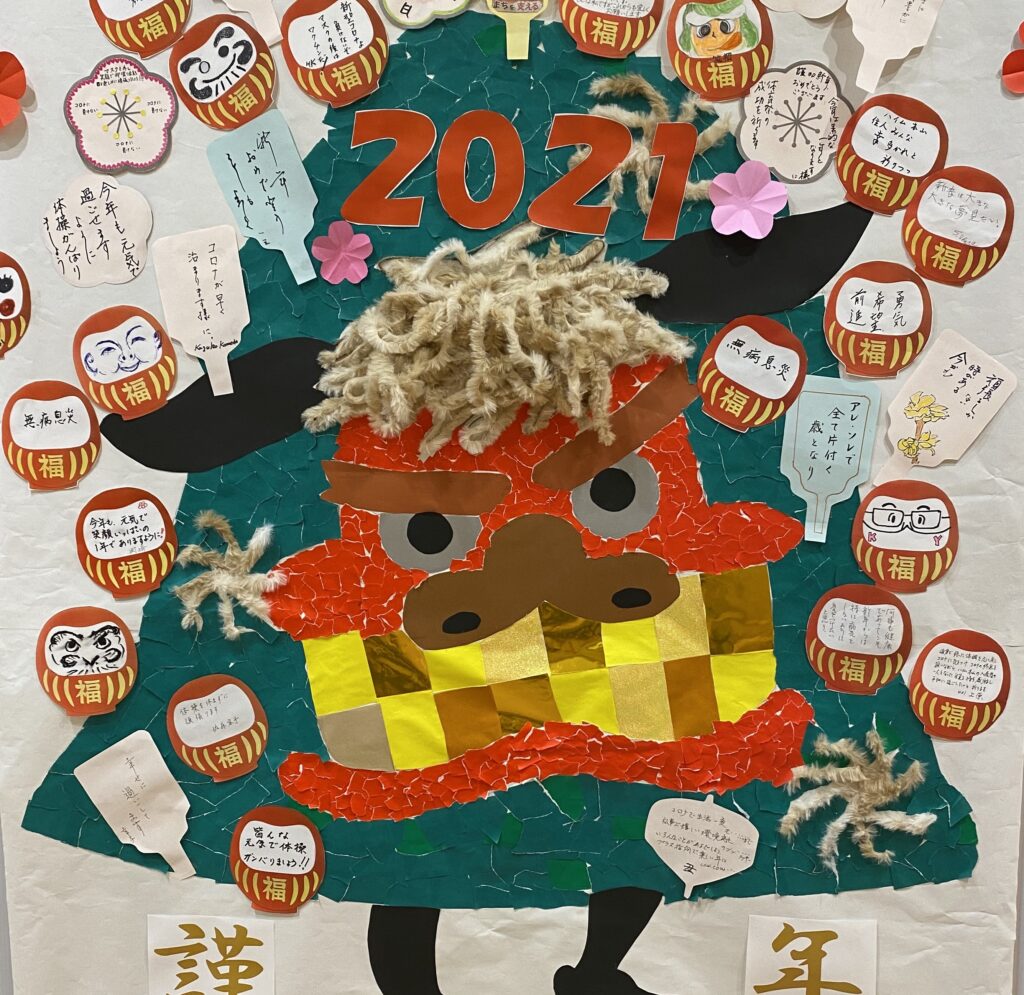
また、「色遣い」とともに「言葉」にも異色さが表れています。専門家ではない私にも、この江戸言葉に対しての歴史的な考察が細かくされていることがわかります。このあまり馴染みのなかった江戸言葉が、決して視聴者に寄り添ったりおもねたりすることもなく、「製作者よがり」にこれでもかこれでもかと出てきます。そこに一切の説明はないので、当然、見ている我々は何のことか意味が分かりません。そこで調べます。そして意味が分かって「なるほど」と思って、「また一つ知識が増えた」と思わされるところに二重の喜びがあって、感動が生まれるという、まさに「にくいね!NHK」と叫びたくなるしくみになっています。
また、大河ドラマには欠かせない「ストーリー展開の面白さ」というところは、最近までは、若干弱かった気もしますが、ここのところの「政治のお話し」が絡んでくると、それも面白みが増してきました。徳川第10代将軍家治の世継ぎに決まっていた西の丸の暗殺とうずまく陰謀、そして平賀源内の最期はめちゃくちゃ感情移入してしまいました。
というわけで、「べらぼう」は最新の17話まで欠かさず見て、しかも次の放送が楽しみでならなくなるという「正の連鎖」にまんまと陥っています。このまま最後まで完走して「新選組」と「どうする家康」の次に三番目の完走記録となるように期待しています。
(写真は4年前に職場で作った新年飾り。江戸文化の雰囲気に近いかなと思って。著作権の関係で実際の番組の写真が載せづらくなったのが悲しい。)
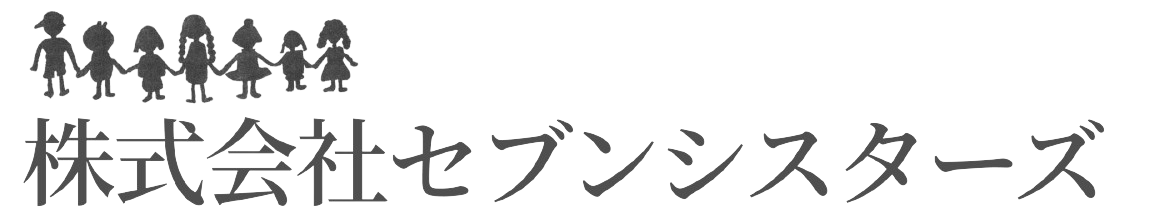








コメント