受付時間 9:00~18:00
#134 「適材適所」
適材適所、岩波国語辞典第五版によると「適材を適した地位・任務につけること」とあります。あれあれ、なんとなく「粗い」解説の仕方ですね。「適材を」ってそのままやん。
今日の「適材適所」は人材のことではなく、英語などの言葉のことです。時間だけは長く英語を勉強していても、なかなかネイティブ、いやそれは無理としても、せめて準ネイティブ並みには会話をしたいが、現実はすらすらと出てくるものではありません。準ネイティブ並みとは、ちょっと目標が高すぎるのじゃないかと言われるかもしれませんが、元来、欲張りな性格なのです。コスパではないですが、勉強してきた時間(コスト)に比べて、あまりに会話の質(パフォーマンス)が低いのは割に合わないと思いませんか。
NOBU(山田暢彦)先生のオンライン英語サロンでもこのトピックはよく上がりますが、そもそもその人の英語を学ぶモチベーションがどこにあるのかというのは、とても大事なことだと思います。私の場合いつも言っていることは「ネイティブと深い話ができる会話力」です。これには当然、話すこと、聞くこと、両方のスキルが相当ないといけないということになります。ですので、朝ご飯を食べながらの毎日30分~60分程度のPodcast英語番組の聞き流し(時に本当に聞き流しだけになっていますが)はもう5年は続けており、また最近ではNOBU先生の1分間即興トークのアクティビティを続けています。これは私にしては珍しく真面目に続けています。それぞれ「聞く」「話す」のスキルを高めてくれるはずだからです。
しかし、問題は「ふりだしにもどる」ではないですが、適材適所ということです。つまり、せっかく覚えた使える表現や、少しレベルの高い単語や、カッコいい言い回しなんか(適材)が、会話の中のここぞというところ(適所)に出てこないということです。「It doesn’t make sense」とか「I can’t afford to~」とか、もちろんこれに限ったことではないですが、せっかく頭で覚えてニンマリしても、実際に出てこなければ、まるで「すばらしいフランス料理のレシピは覚えたのに、一度も作ってないわ」みたいなものです。
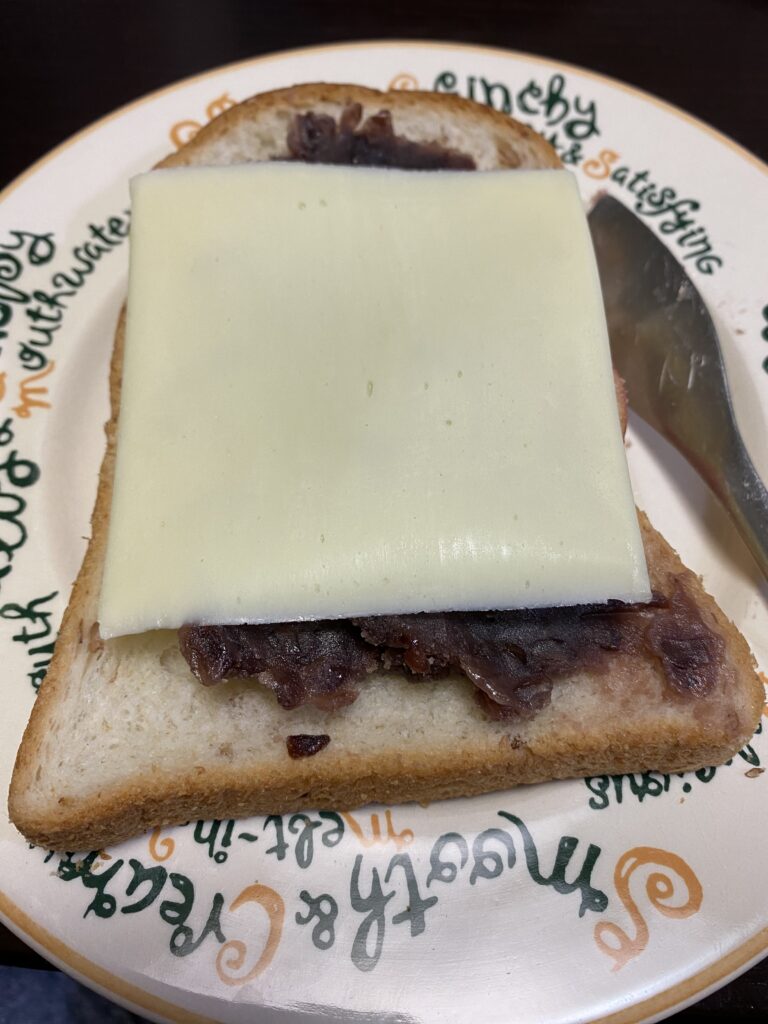
私はなかなかAIと仲良くできそうもないので(食わず嫌いとも言えますが)、やはり英会話なんかは「人間が主導しなくてどうする派」です。そうでなければ、高校時代にN先生の指導の下で頑張って勉強して、外国語大学で勉強して(これは正直に言うと大きな声では言えません)、社会に出てはOJTで勉強して、その傍らBritish Counsilなどの語学学校に通ったりして勉強して、そして今はNobu Connectに入って勉強して、このように「切れそうになりながらも長くつながって勉強してきた」ことがあまりに報われませんもん。
ということで、話は脱線しまくりますが、この「適材適所」を実行するのはどうも語学脳ではなさそうです。いや、これも含めて語学脳なのかな。あとは、これがうまくいかなくなるのは高齢化にともなう認知機能の衰えと関係あるかもしれませんが、じゃあ若い時はよかったかというとそうでもありません。なんでしょう。ひとえに現場経験(実際に現地でネイティブの人と繰り返し会話する)の不足かもしれません。
まてよ、今、英語ばかり考えていますが、これは日本語についても言えますね。適材適所ができていないというのは。ということは私という人間の問題か。
(写真:普段合いそうになり食材でも、パンに乗せて一緒に焼くと意外に美味しくなったりします)
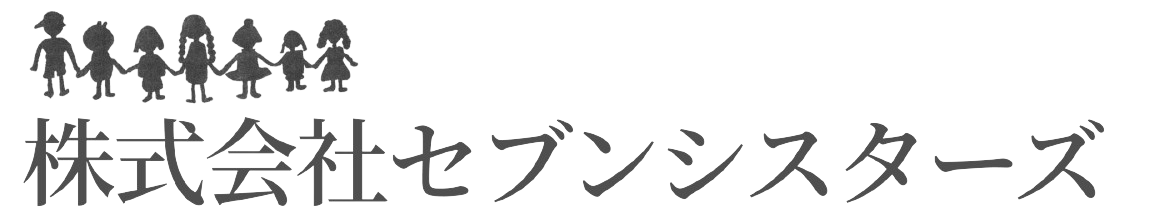








コメント