受付時間 9:00~18:00
#125 「おかたづけ」
何と今日から4月です。最近はあまり流行らないですが、エイプリルフールです。会社は新入社員、学校は新入生が輝く月です。神戸では桜はまだ5分咲きといったところですが、いこいの広場の庭のレモネードの木に新芽がつき始めました。春ですねえ。
さて、ブログを書くことについてスランプだということ(#123 「スランプ大統領」)をカミングアウトしたころから、書くペースはなかなかスローになってきましたが、私にとってのブログは、やっぱり、「文章を書くということ」について、より高みを目指すための挑戦であることは確かなので、ネタがない、モチベーションが減ったとかつべこべ言わずに、書けると思ったその時に書いていきたいと思います。
今朝思ったことであり、そして最近とみに大切だと感じていることは、「何かを使ったら必ず元の場所に戻す」という、まるでお母さんが幼児に言い聞かせているような、基本的ルールです。「おかたづけ」です。そうしないと、「確実に」一日の大半を探しものに費やすという時間のロスが発生します。本当に探し物をしている時間を数えようかと(戒めのために)思ったくらい、気が付けば探し物をしています。探し物をする時間は、普段抱えている仕事が多ければ多いほど、そして身の回りの物品が多ければ多いほど発生しがちになります。
この「探し物をする時間」は年齢を重ねるとともに増えていきもします。何故か。それは記憶力が衰えてくるということに関係していると思います。つまり、①もともと置いてあった場所=長期記憶 ②今、まさに使って放置している場所=短期記憶 ということで、例えば「印鑑はタンスの2番目の引き出しに置いてあるはずなのに、ない!」と言ってアタフタすることが発生するのです。実は、前日の朝、銀行に持って行ってそのまま買い物袋に入れてあったりするのですが、それはすっかり忘れています。短期記憶の欠落です。

こう考えれば、物品、特に大切なものは、「使ったらすぐに元の場所に戻しましょう」という「幼児のためのルール」が歳をとればとるほど大事になってくるのがわかります。でも、これがなかなか面倒くさいんですよね。だから、「今回はここに置いておこう、それを覚えておけばいいか」と思うんですが、それは十中八九、忘れます。そして、また何十分も探し物をして、名探偵のように推理を組み立てて行って、運が良ければ何とか思い出せるのです。
認知症の人にとっての生まれた家が「いつもの置き場所」であり、今、住み替えた新しい家や施設が「新しく使った場所」だとすると、帰宅願望が出るのも「さもありなん」と思えますよね。
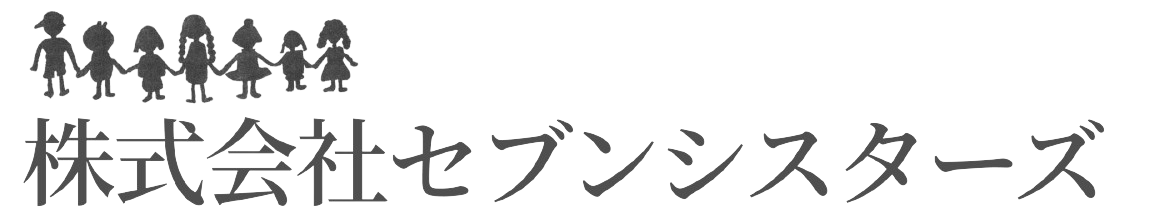








コメント