受付時間 9:00~18:00
#031 「父親学・自分学」
私が「父親」という存在に真に向き合い始めたのは、母が10年前に77歳で旅立ってからなのではないかと思います。私は本当に罰当たりなことに、それまで両親という存在に真正面から向き合っていなかったのではないかと振り返っています。
私はどちらかといえば、母親の方に親密性を感じていましたが、それも本当に寄り添い始めたのは、母がもう動けなくなって、話もできなくなったころからに過ぎなかったような気がします。それまでは、両親という存在にある一定の距離があったような気がします。成人してからは、物理的にも離れて暮らすことがほとんどでしたし、精神的にもいつも一定の距離があったような気がしてなりません。
もちろん、両親に嫌われて育ったということはありませんでしたが、少し「扱いにくい」「よくわからない」子供だったのではないでしょうか。それでも、母親は私にどんどん踏み込んできたように記憶していますが、それも、もともとが天然気質でマイペースの母なので、程よく介入するだけで、私はなんの圧迫感も感じていませんでした。
それが母が逝き、父が残って老いていく。今年は92歳になる。そんな父はこの狭い家の中で私たち夫婦と同居しているのですから、もう否が応でも私と父は真っ向から向き合わないといけません。
父の方からはどうかわかりませんが、私の方からは「親子の関係性」という初めて真剣に考えたテーマの中で、初めて「近い距離から、父との双方向の関係性について毎日、課題として向き合っている」ような気がします。
父は、昔からとても面子を大事にする人でした。表面的にプライドが高いようには見えなくても、心の奥の見えないところのプライドは誰にも負けないような人でした。だから、「自分が悪く言われる」「叱られる」「認めてもらえない」ということに異常に反応し(そうならないようにプラスに動くのではなく、そうされないようにマイナスに防御する)、その一つの手段として、非常に外面をよくしていました。父と接する人のほとんど誰に聞いても「穏やかでやさしい人」「人のお世話をよくする人」という言葉が返ってきます。
それが、今は自分の老いと、そしてそれに付随するプライドと闘っています。プライドを保つために「そろそろわしもぼけて来たかな」「ついにこんなことがわからなくなってきたか、アホや」と自分自身を防御し、声に出してアピールしながら闘っています。意地悪な息子は、様々な言動にツッコミを入れるのですが、父は表面上、理解したふりをしながらもまったく聞こうとしないことが多いです。
父にしてもそうですが、息子はもっとたちが悪い。父を鏡に自分の姿を映して反省することが日々あります。「言い過ぎだ」「親父はおやじという部分をもっと認めるべきだ」というもう一人の自分の声と闘っています。また、父から受け継いだといえば、傲慢になるかもしれませんが、外面はどうなのかは別として、内面のプライドの高さはダイヤモンド鉱石のように固いのは確かですので(私の一番身近な家族に聞いていただければわかります)、人のことを言えるかというもう一人の声もあります。
自分の「父親学」は、そのうち「自分学」として向き合うことになるのでしょう。そして、「老いる」という永遠のテーマに関しては、常日ごろ「早いうちから老いを意識し、老いと寄り添い、自然に老いて行く」をスローガンにしていますが、果たして自分が本当に老いたとき、そんな風に達観できているかが見ものです。

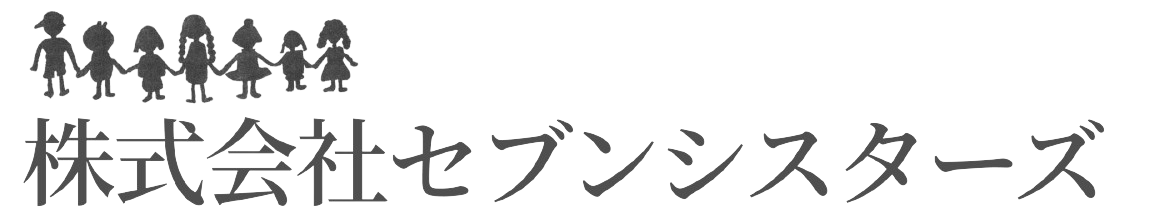


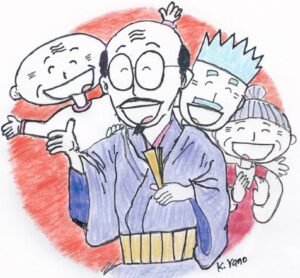





コメント